ケーススタディ
有力都市銀行A社
事業戦略の構築
- 中小企業の融資市場における顧客動向、競合動向、A銀行のポジション等を精査し、セグメンテーション及び各セグメントの攻略プランを立案
- 潜在市場サイズ、顧客の生涯価値、競合時の勝率、打ち手による収益の差異、将来収益の予測とNPV(現在価値)など、あらゆる観点からマーケティング情報を「収益という数字」に換算し、経営判断に耐えうる戦略オプションを策定
- A銀行において不良債権処理が峠を越しつつある中、競争の方向は“財務の健全性”から“収益性の確保”へと大きくシフトしていた。
- 特に、大企業向け企業金融ビジネスの収益が低迷する中、中小企業市場の重要性が増していたが、当市場は競合がひしめく激戦区となりつつあった。
- このような市場において、競合から顧客を奪取し、自らの顧客を守り、また新たな顧客を生み出していくために、顧客のことを深く理解し、本格的なマーケティング機能を事業モデルの中に組み込み進化していくことが必要であった。
A銀行は、本プロジェクトを経て、顧客の事業価値へのインパクトを計数化することで、適切なターゲッティングを行い、市場環境・顧客ニーズに適合した新たな成長モデルを構築・実行することができた。
その結果、年間業務純益ベースで3.2倍ものインパクトを生み出すこととなった。
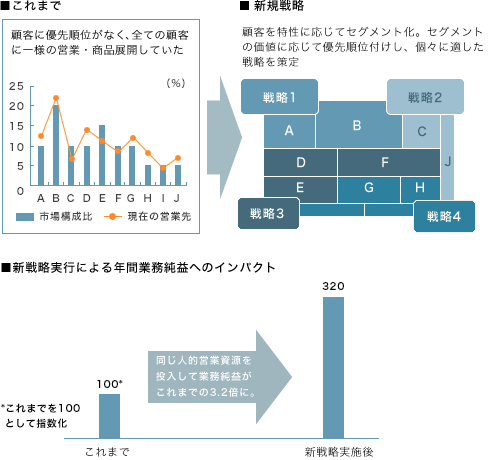
そもそも顧客はどの様な企業か?
顧客の金融機関利用動向、ニーズや不満、さらに、顧客の属性・置かれた状況による心理・行動の差異等を徹底的に掘り下げて分析を実施。そのために、グループインタビューや個別インタビューを通じて仮説を構築し、大規模な顧客サーベイにより定量的に捉えた。
- 分析項目例
- 企業規模、業界、経営者の特性
- 取引金融機関、使い分け、借り換え経験
- 借入商品・額・金利・期間
- 取引金融機関の評価、新たな商品ニーズ
- 資金ニーズの使途や金額、発生頻度等々、数百に及ぶ項目から分析
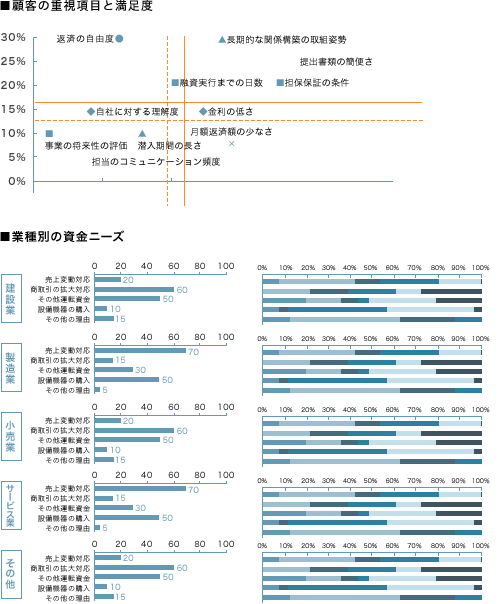
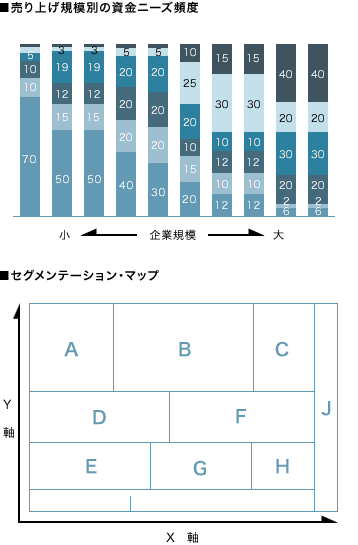
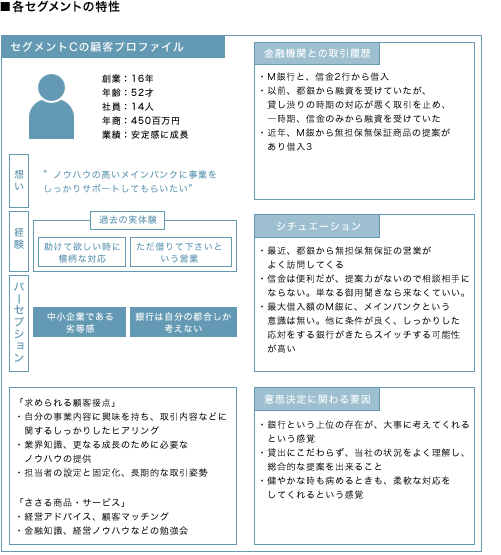
限られた経営資源で、最大の効果を発揮をするためにはメリハリのあるターゲッティングが必要である。
セグメントの優先順位付けは、各セグメントを攻略するコスト・労力と、(将来に渡って)得られる収益、さらには今後の自社にとっての意味合い等によって評価することが有用である。
本プロジェクトでは、まず、各顧客に資金ニーズが生じた際に、競合と比較し、自行が融資実行を獲得できる可能性=勝率を、自社の営業モデルと顧客との取引関係から4つのパターンに分けて算出した。
この勝率を基に、各セグメント毎での顧客獲得に掛かるコストとリターン、将来に渡って得られる収益を個別にシミュレーション*し、顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)を算出した。
これらの基礎データから、各セグメントで期待され得る収益の現在価値を割り出し、自行の事業価値向上に対する貢献度の高さによってセグメントの優先順位付けを行った。
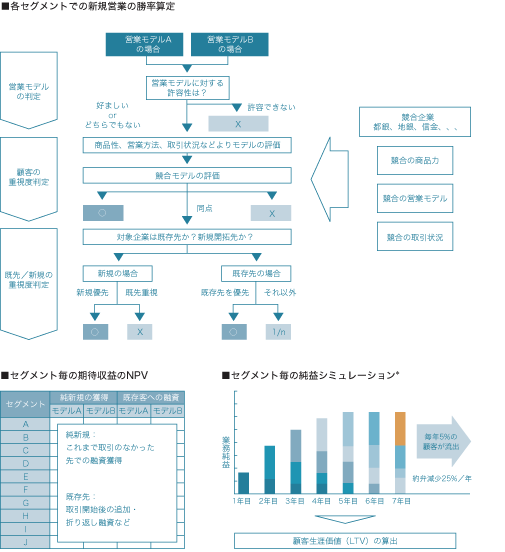
新規顧客を奪取し、市場でのパイを拡げていくことと同時に、ストックビジネスの金融業においては「獲得した顧客のリテンションを如何に図るか」ということが極めて重要となる。
実際、適切なリテンションによりどの様な差異が生じるのかシミュレーションを試みると、5年間で、残高で30%、経費率で10%もの開きが生じることが明らかとなった。
この点についても顧客サーベイを基に、スイッチ前の金融機関に対する不満とスイッチ先での満足度、スイッチした顧客の特性、実際のスイッチ率などを各金融機関毎に分析し、A銀行ならではの有効な打ち手を考案した。
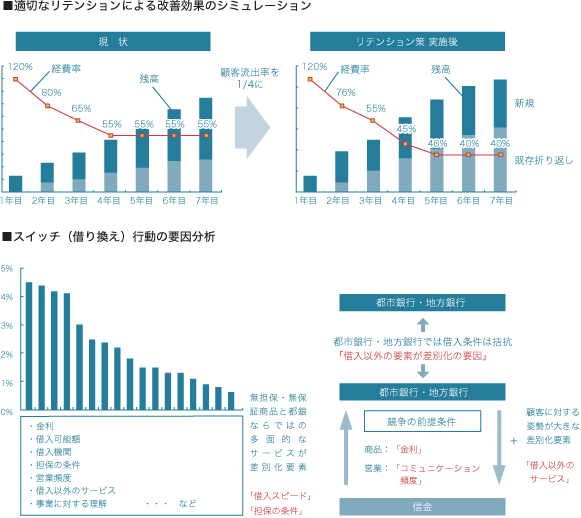
これまでの市場・競合環境とターゲット顧客層の分析に基づき、A銀行が取るべき戦略上のポジショニングを構築。現状の立ち位置から解決すべき課題と採るべき施策を明らかにした。
本ケースでは、これまで当該市場において主流を占めていたリレーションシップ・バンキングvs.トランザクション・バンキングという二元対立論を超えた、これまでにない機軸による新たなポジショニングを導き出し、力強い成長モデルを構築することに成功した。
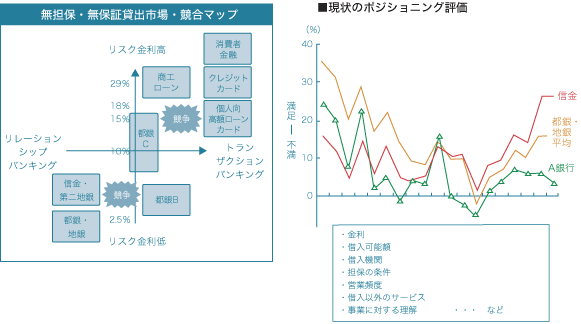
但し、実際に事業コンセプトを実行レベルに落とすためには、施策を整理・具体化することが必要であった。
新たなポジショニングを機軸として、それぞれのターゲットに応じた、商品・金利、営業、プロモーション、チャネル、オペレーションなど具体的施策を策定した。
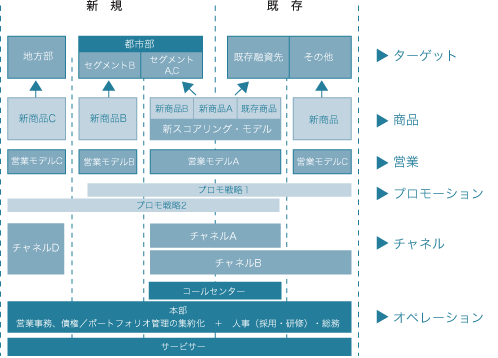
外食チェーン店B社
マーケティング戦略
- 新たな成長の方向性を検討する上で、顧客が当社および競合店をどのように利用し、何を求め、またその背景にはどのような心理が働いているのか、顧客の深層を構造的に分析・理解
- これまでの成功モデルと今後のあるべき姿を明らかにし、当社の強み・想いと紡ぎ合せ今後の成長戦略の礎を構築
- これまで順調に成長してきたが既存店での売上が頭打ちとなり、新たな成長を実現するための方策について、社内においては多様な意見がぶつかりあっていた(その多くは、表立ってではなく水面下で話されていた)
- また、企業の重要な戦略判断が、声の大きな人、権限を保有する個人の経験や勘によってのみ決定されるという事態が生じており、顧客の声、科学的分析に基づく意思決定が求められていた。
- 食材調達に関する外部環境が変化する中、新たな成長の方向性に関して、微妙な舵とりが求められる状況にあった。
本プロジェクトの結果、外食チェーンB社は以下のような成果を得、踊り場から脱し新たな成長へのスタートを切ることができた。
また、本プロジェクトでは、B社の有望な若手社員との合同チームを組成した。若手社員が積極的に参加し、マーケティングの意味合いと効果を肌で感じ、スキルを身につけたことで、自力での更なる成長・連続的進化を実現できる礎が作られたことが、本プロジェクトでのもう一つの大きな成果であった。
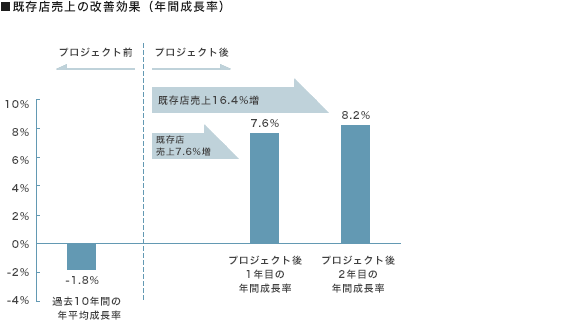
まず、対象商圏においてB社がどこで顧客を取りこぼしているのか、モレ分析を使ってみてみると、90%を超える高い認知率を誇り、利用経験者割合も非常に高いことが判明した。
このことから、現在B社が認知率向上ために多大な広告コストを掛けていることはもはや効率が悪く、むしろ利用経験者のリテンションを如何に図り、現在の利用客からの売上を如何に伸ばすかがより重要な課題であることが明らかとなった。
また現在の利用者の内訳を見ると、人数ではライトユーザーが7割を占めるのに対し、売上構成比では、 ヘビー/ミディアムユーザーが7割以上を占める顧客であることが分かった。
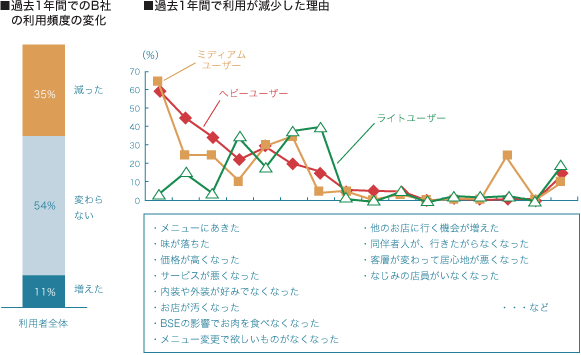
一方、過去の顧客変動を見ると、増加よりも減少が多く、原因を分析するとヘビー/ミディアムユーザーは、メニュー内容に対する不満(定番メニューがない、味が落ちた、価格が高くなった)が強く、ライトユーザーは中心メニューそのものへの嗜好が減退していることが大きな要因となっていた。
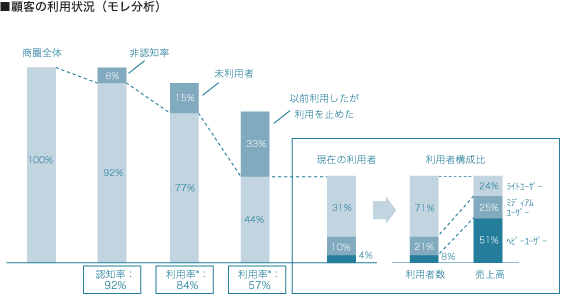
それでは、B社が顧客の獲得を図っていく上で競合となるのは誰であろうか?
B社社員の方々にインタビューをすると、一様に同業他社(類似メニュー)のチェーンを挙げていたが、真の競合は同業他社のみではない。
既にファミレスは同業他社以上の競合であるし、「外食」という視点から見れば他のメニューの店が、さらに「食事」という観点から見れば中食や家庭の食事が競合と認識されるべきである。
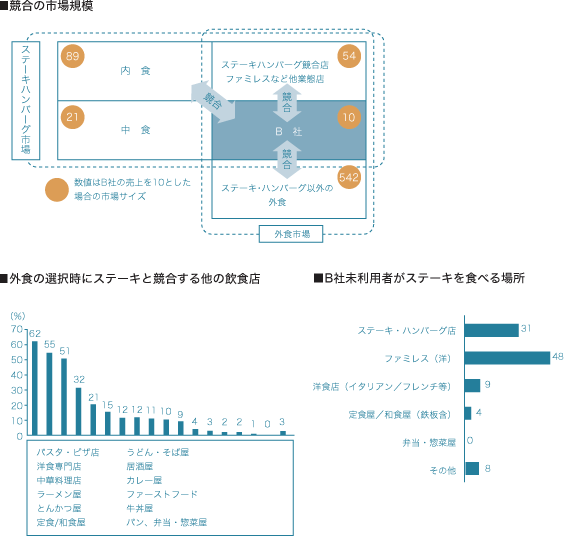
また、商圏内でのB社中心メニューの外食需要に対し、B社は、どこで競合に勝ち、どこで負けているのか?
顧客の外食利用シーン毎に市場サイズと、その中でのB社のシェアを市場調査を基に算出した(当然のことながら、このような情報は他では絶対に手に入らない、B社のみの特別なものである) 。
このようにして見ると、まずこれまでB社が強いと考えられていた最大の市場であるディナーでの家族利用で実はシェアが低い、という問題が明らかとなった。
また、これまで平日夕食の顧客数が少なくても「どこでも外食はそのようなもの」という考えが蔓延し、顧客獲得に力を入れてこなかったが、このように数字でみると、本来達するべき平均シェアのラインを大きく下回り、実際には競合に顧客を取られていることが見てとれる。
このように、数字をもって市場環境を理解することで、自社の置かれている状況と対処すべき課題が明確となった。
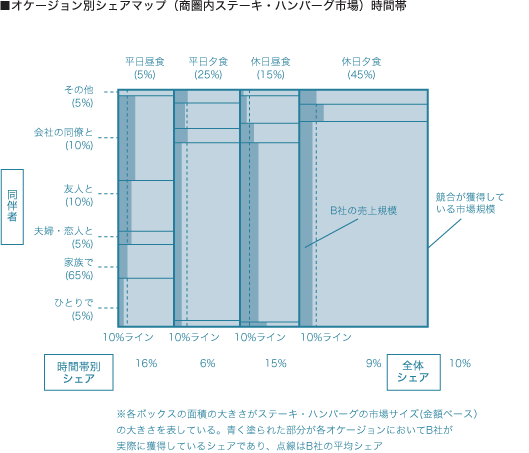
では、それぞれの顧客層をどのようにして攻略していくか。
ディナーでのファミリー利用の増加を図るためには、人数ベースでは最大のライトユーザー/未利用者の取り込みが重要となる。
そこでまず、顧客が外食店を決める際の意思決定者、意思決定プロセス、意思決定基準はそれぞれどのようになっているかを分析した。すると、面白い構造が見えてきた。
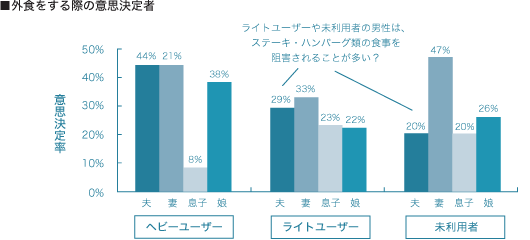
ファミリーで外食に行く際、ミディアム・ヘビーユーザーは夫のお店選択の決定権が強い(但し、お父さんも娘には弱い)のに対し、ライトユーザー・未利用者の男性の意思決定権は女性よりも低い。
一方で、メインメニューαの場合、男性が食べたいと言っても女性に反対されるケースが多いが、新メニューラインβであれば逆に女性が食べたいというケースが多く、かつ反対されることも少ない。
以上のことから、B社のライトユーザー/未利用者を攻略する上では、女性に新メニューラインβを訴求することが有効であるとの考えが導き出された。
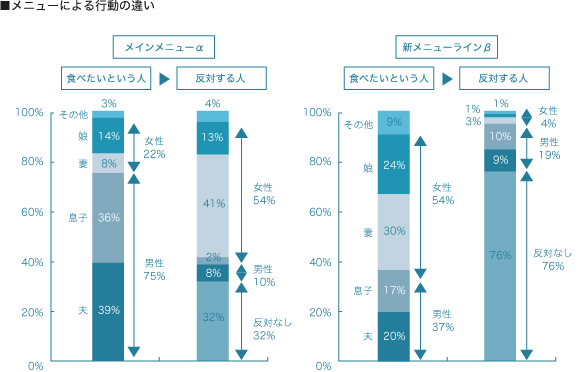
一方で、ファミリーのライトユーザー等を獲得するために、これまでのメインメニューα中心の店からフォーマットの転換を図った場合、現在の売上を支えるヘビーユーザーの利用はどのように変わるだろうか?
仮に、女性を取り込みやすいように新メニューラインβの強化やその他メニューの充実化を図ると、図表の通りヘビーユーザーの多くからは支持を得られないという結果が明らかとなった。
では、B社は、フォーマットを変更してヘビーユーザーの利用が減る替わりにライトユーザー等を獲得するべきであろうか、それとも今のまま現状を維持すべきであろうか。
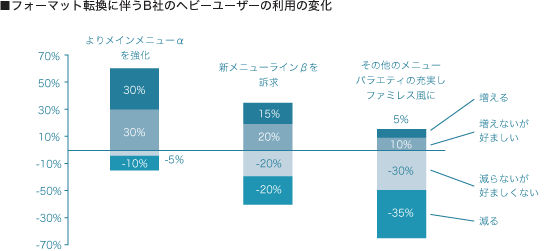
この命題を打ち破るヒントが、顧客調査の中に埋もれていた。
ヘビーユーザーは、ファミレスなどへのフォーマットの変更に対する反発は強いものの、ファミレス的な要素となる個別の施策に対してはむしろ肯定的であるということだ。
すなわち、B社のヘビーユーザーは「B社らしさ」がなくなることを嫌うのであって、メニューバラエティや利便性が上がる、ということに否定的なわけではないのである。
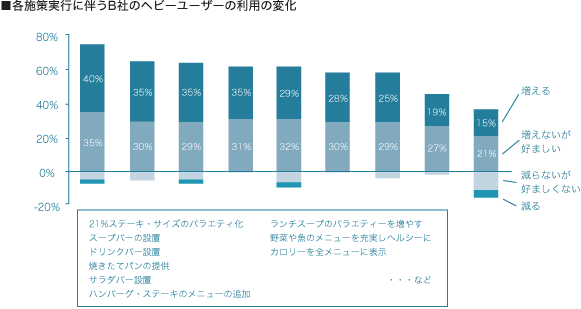
「新たなポジショニングの確立」
以上のことを踏まえ、今後B社はどのような成長戦略を描くべきであろうか?
これまでB社では、相容れない3つのポジショニングのうちのいずれをとるのか、という議論がなされてきた。
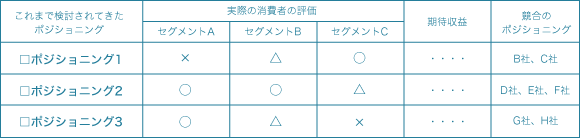
このような命題に答えるため、各ポジショニングを選択した場合に、B社は何を得ることが出来、何を失うのか、そのインパクトはどの程度なのか、そのポジショニングはB社の企業理念・ミッションに合致するのか、といった観点からそれぞれのオプション(選択肢)を評価・検討した。
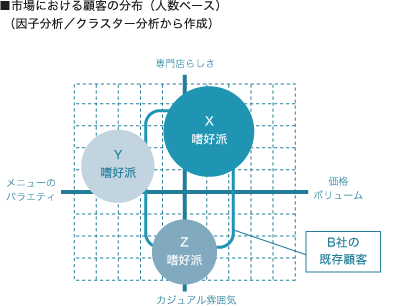
大手プロバイダC社
進化型CRM
- 全対象消費者のうち、特に優先度の高かった既存顧客向けのマーケティング全体戦略の策定。
- データベースマーケティング/CRMの徹底活用によるマーケティング戦略の継続的進化を図る仕組みの構築。
- インターネットの普及に伴いISP事業者が乱立し、市場での競争が激化。
- 個人向けを主体とするISP事業者として勝ち残るために、如何にして上位サービス・コンテンツでの差別化を図り、事業を強化するべきかが喫緊の課題となっていた。
- 当ISPの顧客基盤は厚く、新規顧客の拡大よりも、既存顧客のリテンションとARPU(ユーザー1人当たり平均収入:Average Revenue Per User)の向上による顧客生涯価値(LTV: Life Time Value)を中心としたビジネスモデルへの転換が求められていた。
本プロジェクトを経て、C社は顧客中心モデルへの大きな変革を果たすことできた。
その成果の一旦として、顧客満足度、ARPU、解約率、プロモーションの反応率・成約率等において飛躍的な改善効果が見られた。
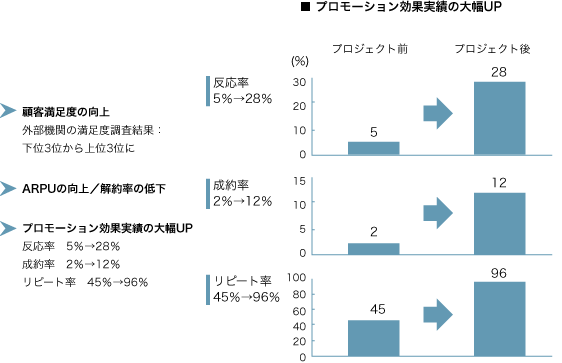
これまでC社は、顧客志向性が欠如していたことから、顧客の顔が見えておらず、顧客に対する適切なコミュニケーションもできずにいた。
例えば「収益のみが目標となり、顧客満足に関する指標・目標がない」ため、「ホームページに書いてある、分かるはず、調べたらすぐ分かる」という顧客に対する勝手な思い込みが生まれていた。
そのため、顧客にとって「サービスの理解がすすまない、ISPの事が良く分からない」といった状態が生まれ、その結果ARPUの低迷・解約率の増加を招き、顧客生涯価値(LTV)が大きく減少するという悪循環に陥っていた。
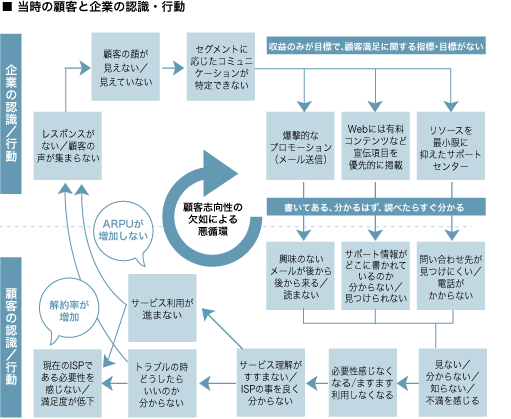
顧客中心モデル実現に向けての第一歩は、顧客セグメンテーションである。まず、特に優良な顧客層と、解約危険性の高い顧客を選別し、優先順位付けをする。そして顧客対応の方向性を組織全体で理解・共有し、顧客層毎に最適なコミュニケーション、あるべきサポートを行っていくことが重要となる。
本ケースでは、顧客生涯価値(LTV)を顧客の継続利用意向とARPUに分解し、縦軸と横軸に設定することで、LTVを基準とした顧客の優先順位付けを可能とした。
一方で、コミュニケーションは密なほどARPU及び継続利用意向にプラスに働くが、セグメントによって求めるサービス、刺さる表現は異なるため、主要媒体であるメールは、セグメントに応じた設計を検討した。*し、顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)を算出した。
また、コンタクトセンターを始めとしたサポート体制は、総合満足度へ大きく影響しており、不満を持った顧客の継続利用意向は大きく下がってしまう。各部門一丸となった入電件数削減の工夫で応答率を改善すると共に、コンタクトセンターの処理効率改善で解決件数を増加させ、サポート満足の向上を図ることでLTVの増大を図った。
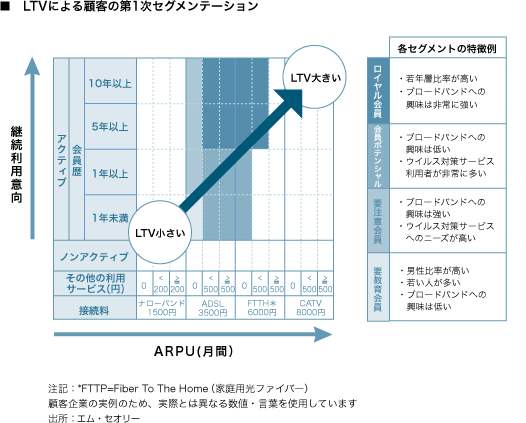
マーケティングの実践に当たっては、トップダウンアプローチのマーケティング戦略に加え、ボトムアップアプローチであるデータベースマーケティングの両輪を稼動させることが有効である。
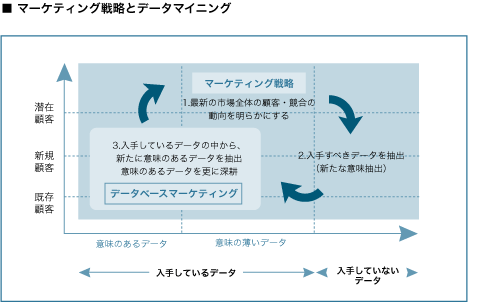
「進化型CRM」
また、データベースマーケティングの力強い運用によって、CRMは真の価値を実現し得る。
CRMというと、これまでは主として顧客対応業務・管理の「効率化」を目的して高額なITシステムを導入し、十分な成果を上げることが出来なかった事例が多数存在する 。
しかしながら、そもそもCRMの真の価値は、顧客情報の活用レベルの飛躍的向上を図り、営業収入拡大などの攻めのマーケティング戦略実行においてこそ力を発揮するものである。
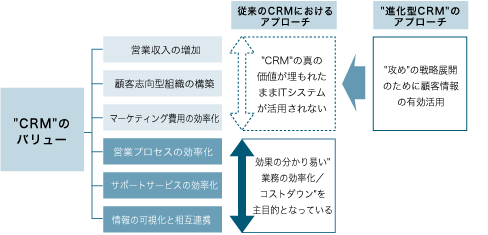
データベースマーケティングの推進に当たっては、顧客購買行動などの収集したデータに基づくデータマイニングにより、詳細な顧客行動の予測を行うことが重要となる。
本ケースでは、顧客へのクロスセル・アップセルの増加を促進するために、顧客層毎にどのようなコンテンツの購入率・並売率が高いのか、何のコンテンツを買った人が次にどのようなコンテンツを買う(買わない)確率が高いのか、というような分析を実施し、高効率なコンテンツ戦略を策定した。
また、ブロードバンドへのアップセルができる可能性が高いポテンシャルユーザーを決定木分析によって分類・特定し、ターゲット毎にプロモーションの費用対効果を検証することで、無駄なコストを削減し効率的な活動を実現した。
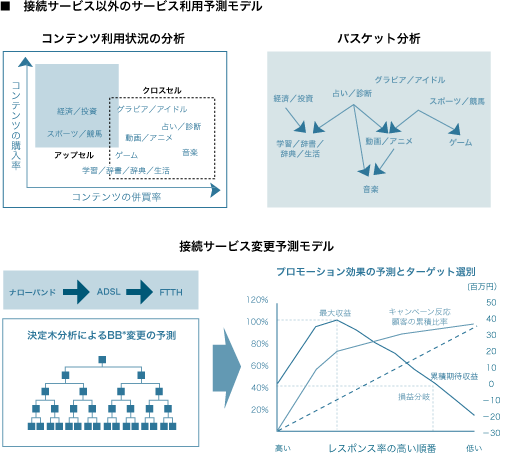
これまで見てきたような一連の活動に持続的・継続的に取り組むことで、連続的進化を実現し、顧客生涯価値、さらにはC社の企業価値の飛躍的な向上を図る。
本ケースでは、既存顧客のセグメンテーションとターゲッティング、ポジショニングに基づきマーケティング戦略を紡ぎ上げ、顧客へのコミュニケーションプランの策定・実行、およびそのフィードバックによって戦略を進化させる仕組みを構築した。
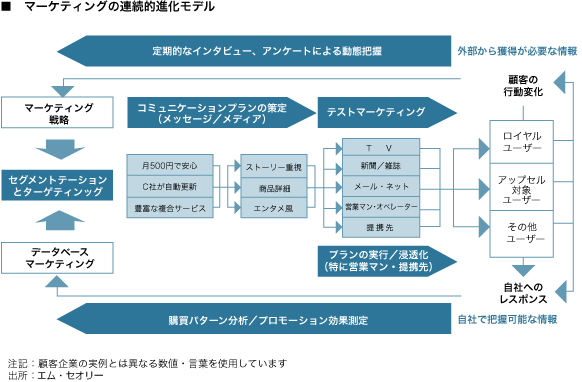
中堅企業D社
M&A
- 中堅企業D社(サービス業)の年商は300億円で、翌年のIPO(株式公開)に向け準備中だった。
- ある日、同業界で上場会社であるX社の株式30%が、近年の業績不振のために入札方式で創業者一族から売却に出るということが判明した。
- D社にとっては、一気呵成に事業拡大できる絶好の機会であり、社長は直ちにエム・セオリーと共同でM&Aチームを結成し検討に入った。
社長の決断が求められた課題
X社の株価は現在800円。800円強の入札価格で落札できるだろうか?それとも1,000円以上の入札価格が必要だろうか?
- チームの提案 : 1,200円で入札する
- 同業界の中で最もX社と事業内容が近いD社は、X社に対するシナジー効果が高く、通常想定されるシナリオで1,200円、最も成功するシナリオでは1,600円を提示することが可能(図1)
- D社以外の同業界他社の場合、D社ほどのシナジー効果は見込めないため入札価格は最高で1,100円台後半までしか提示できないと考えられる(図2),200円、最も成功するシナリオでは1,600円を提示することが可能(図1)
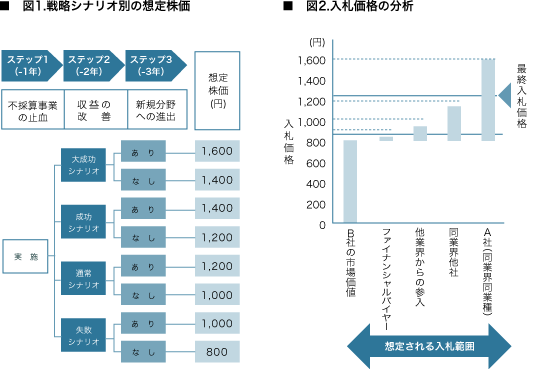
経営の主導権を獲得するために、株式取得を何%にすべきか?34%?51%?それとも67%?
- チームの提案 : X社株式の過半数の獲得を目指しTOB*を行う
- X社の現役員全員が合併に強く反対しているため、取締役会の支配を確実にするためには、51%以上の株式を取得し新たな取締役を任命することが必要(図3/図4)
- 株主総会への参加率が低い個人投資家の比率が高い点や、中立・友好的な株主の存在を踏まえると、合併決議を株主総会で可決できる可能性が高い(図3/図4)
- D社の借入余力は最大でも50億円であり、67%の株式を取得するためには、他社資本に頼る必要がある(図3/図4)
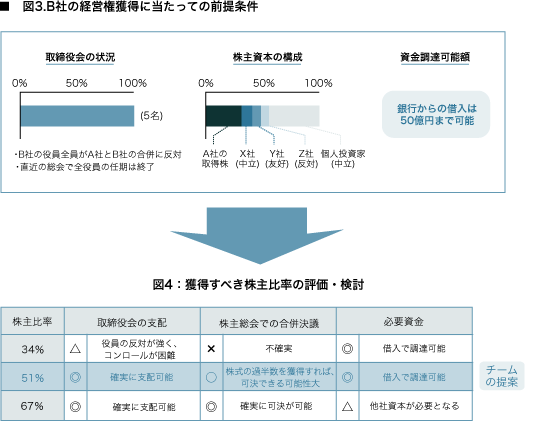
結果 : TOBを実施した結果、過半数の株式を取得し経営権を獲得できた。また、株主総会において、合併の決議も三分の二以上の賛成を得ることができた
※上場企業の株式の34%以上を買い付ける場合にはTOBを行うことが義務付けられている。
注: 本事例では、課題の論点を明確に、わかりやすくするために、実際の分析よりも簡素化して表現しております。
又、顧客企業の実例のため、実際とは異なる数値を利用しています
現在進行中のIPOの準備をそのまま続行すべきか?それともX社との合併を優先してIPOは一時中断すべきか?
- チームの提案 : X社株式の過半数の獲得を目指しTOB*を行う
- IPOと合併のどちらを優先するかを意思決定する必要があった
- 限られた社内の人材だけでは、IPOと合併の実施を同時に行うことは困難であり、どちらかを選ばなければならなかった
- どちらのケースの方が、D社株主に配分される株主価値がより大きくなるかを検討する必要があった
- それぞれのケースにおいてD社株主に配分される株主価値を算出した結果、合併の実施を優先した方がD社の株主に有利であることが明らかになった
- D社株主に配分される株主価値は、合併の実施を優先したケースで240億円、IPOの実施を優先したケースで215億円(図5)
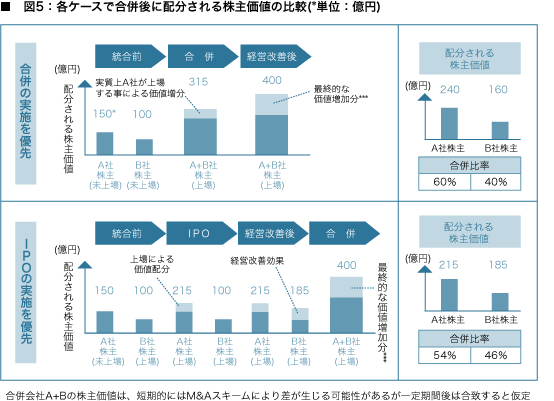
結果:合併の実施を優先したことは、D社株主にとって正しい決断となった
- 合併決議から統合するまでの1年間で、 X社の株主価値は、想定値よりも大幅に上昇していた
- その結果、合併を優先した場合、D社株主に配分される株主価値は300億円に上昇した
- 一方、IPOの実施を優先した場合、D社株主に配分される株主価値は300億円を大幅に下回る215億円となっており、合併の実施を優先した事は、D社株主にとって正しい決断であった(図6)
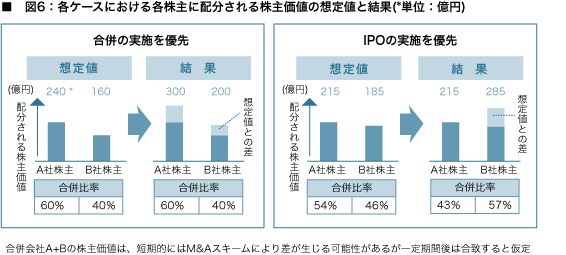
X社の買収話を聞きつけたファンドから資金提供とM&Aスキームの提案がなされた。果たしてファンドの提案は、D社にとってベストな選択なのだろうか?
- チームの提案 : これまで検討したM&Aスキームの方が、合併後も経営権を確実に掌握でき、合併後に配分される株主価値も大きく有利
ファンドが提案するM&Aスキーム
- X社を100%子会社化する
- 完全子会社化するためには借入だけでは賄えないため、50億円をファンドが増資
- 増資の結果、D社に占めるファンドの株主比率は30%となる
- X社を上場廃止にした後にD社と合併する
- 合併後の統合プロセスが一段落ついたところで改めて新会社として上場する
チームが提案するM&Aスキーム
- X社の株を51%取得する
- 株主総会で三分の二以上の賛成を得て合併を決議する
- 必要資金は、銀行からの借入で対応する
- IPOよりも合併の実施を優先的に行う
- 早期に合併を実施することで、X社の上場を維持した場合の株価変動リスクを最小限に抑える
各スキームの評価にあたっては、「X社の経営権の獲得と合併後の経営権の掌握」と「D社株主に配分される株主価値」の二点が大きな論点となった
「X社の経営権の獲得と合併後の経営権の掌握」の観点からは、チームで検討してきたM&Aスキームの方が優れているといえる(図7)
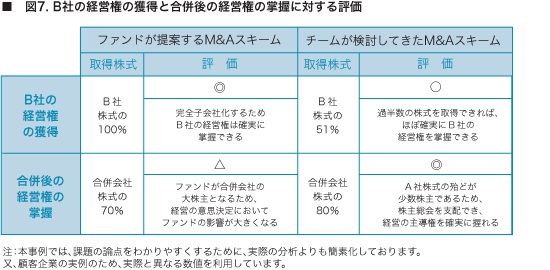
D社株主に割り当てられる株主価値は、チームで検討したM&Aスキームの方が40億円高い(図8)
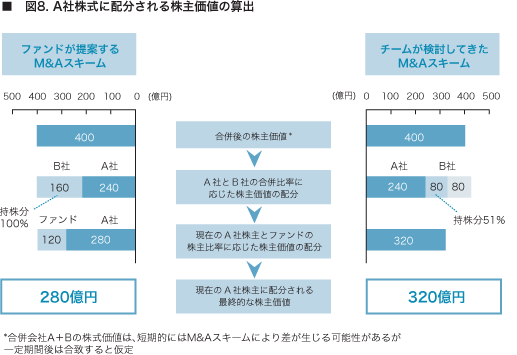
結果 : チームが検討してきたM&Aスキームを採用したことにより、不必要な資金調達を行わずに最適なM&Aスキームを実施することができた
